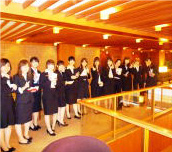| 櫻川 幸恵 准教授 |
| 株式会社グッドバンカー取締役社長の筑紫みずえ様が講演をしてくださいました 上記の講演は生活環境マネジメント学科展開科目の「資産運用論」で、12月3日に行われました。 テーマは「SRI-社会的責任投資が変える世界の姿と日本の女性」です。約100名の学生が聴講しました。 株式会社グッドバンカーは、筑紫さんが創業した会社であり、エコファンドと呼ばれる環境に配慮した企業を対象として投資をおこなう金融商品を日本で初めて開発した会社です。 |
|||
|
|||
・投資は「もうける」ためだけではなく、社会をよりよくするための手段になる。 ・投資とは、株式投資だけでなく、預金をする、保険に入るといったことも含まれる。 ・女性の価値観が、今後、社会をつくる際に大きな影響力をもつようになる。 といったことが話されました。 学生の反応をみると、SRI(社会的責任投資)を身近に感じるとともに、自分の選択が自分も社会も豊かにする可能性をもっており、正しい選択ができるよう学んでいく必要性を感じたようです。 |
|||
ニューヨーク便り 2013年3月31日
NYから帰国した。長かったようであっという間の1年だった。
昨年の4月にNYに来た当初、Imagine:How creativity works (著者J. Lehrer、出版社Houghton Mifflin Harcourt )という本をある先生から薦められた。この本の内容は、副題が示すように、どのように状況でCreativityが生み出されるかを、個人レベルおよび集団レベルそれぞれについて記述したものだ。著者がNY在住であることもあり、個人レベルでの事例はNYで活躍した人を取り上げていることが多い。経済学はアメリカが本場だ。どうして優秀な人たちがここで生み出されるのか、本の内容は、それを考えるヒントをくれたように思う。
大学のセミナーの報告は、大学院を出て間もない先進気鋭の人からノーベル経済学賞を取った人まで多種多様だ。一様に真摯に謙虚に報告し質問に答えていく。そこには「ノーベル経済学賞をとった」とか「俺は大物だ」いうようなおごりは一切ない。報告される論文はいずれも、このテーマで取り上げるべき内容はすべて押さえる、といった迫力がある。セミナー中も終わった後も質問攻めになっている。ただ、否定的な意見はほとんどなく、どういった設定なのか、その設定に無理がないか、といった確認と、そこからのインプリケーションの理解が中心だ。大学の教員、各国からきて学ぶ大学院生や客員研究員が、それぞれの知見から密度の濃い議論を繰り広げている。そこからは、分析対象を相対化し普遍化することによって、問題を理解し共有しようという印象を受ける。こういった姿勢は、多様な人々が構成する社会であるからより一層強いのではないか、と感じた。相互に理解するためには、いわゆる「あうんの呼吸」は通じない。お互いの共通言語は経済学だけなのだから。多様性が普遍的な理解を生み出し、普遍的な思考が個別の理解を助けるといった流れが、ここにはあるように思う。そして、学者同士の競争はとても厳しいが、それは切磋琢磨の密度が濃いという印象だ。
都市経済学者のE. Glaeserはその著書Triumph of the City(出版社Penguin Book)で、都市の多様性が新規性と創造性を生み出すことを指摘している。NYには様々な創造的なものがあふれている。学問の世界をそうだが芸術の分野もそうだ。「NYはアメリカではない、コスモポリタンだ。」という人もいるが、まさにその通りだろう。人々は街からいろいろな刺激をもらい続ける。そして、自由がある。多様なものに触れていくうちに、これはこういうものだ、と知らずに縛られていた思考から解き放たれていく。
私がこの1年で学んだもの感じたものは計り知れない。受け入れてくださったColumbia大学と、送り出してくださった跡見学園女子大学に心から感謝を申し上げる。
ニューヨーク便り 2013年1月
お久しぶりです。
NYの街は、12月のホリデーシーズンの華やかな雰囲気から、落ち着いた雰囲気に変貌しました。
先週のNYは、1週間ずっと、最高気温でさえ氷点下の極寒でした。11月くらいでも埼玉や東京の冬と同様の寒さの日も続いており、私としては、すでに日本の真冬の格好をして出かけていたのですが、知り合いからは「1月や2月はもっと寒いからね」と念を押されていました。本当にその通りです。今は、ダウンコートにニット帽、極厚の手袋と、完全防備で外に出ても、寒いというより痛いという感覚に襲われます。でも、寒さには慣れるものです。今日は最高気温が3℃くらいまで上がったので、寒さを気持ちよく感じながら外を歩くことができました。
お気に入りの場所にも変化がありました。夏にGreen Marketという NY近郊の農家や生産者が新鮮な食材を売りにくる屋外で開かれている市場に、知り合いになった方に連れていってもらってから、そこで食材を買うことが私のお気に入りの週末の過ごし方の一つだったのですが、先日久しぶりに行ってみると、緑色の野菜がなく根野菜の類ばかりになっていました。寒すぎで葉物野菜は取れないのですね。スーパーマーケットでは、1年中なんでも売っているのですっかり忘れていましたが、食物の旬を実感します。でも、品ぞろえは減ったとしても、寒さの中、この市場にお店をだし、たくさんのお客さんが買い物している様子をみると、NYのエネルギーを感じます。
2013年1月27日
ニューヨーク便り 2012年7月
NYにきて、早いもので、もうすぐ4か月がたとうとしています。
MBA(経営学修士)のサマーコースの授業を聴講したり、NY FED (ニューヨーク連邦準備銀行[アメリカの中央銀行制度を司る連邦準備制度を構成する銀行の一つ])を見学したり、充実した日々を過ごしています。
こちらに来て感じるのは、理論ベースに物事の動きをとらえようとするという姿勢の強さでしょうか。経済学の考え方を、ある種の共通言語として、現実の経済の動きの理解を試み、さらに、理論的に考えると今後何が起こるのか、どのような政策が望まれるか、と考えていく。そういった思考方法が、ビジネスマンやマスコミの人々にも強く身についているように感じます。学生もそういった思考方法を身に着けようと一生懸命です。もちろんNYが世界に金融の中心であり、金融取引が経済取引の中でもっとも経済理論の想定する世界を具現化しているということはあるとは思うのですが。
さて、まったく別の話です。先日、あるオンライン通販会社に、飲料水の宅配を頼みました。私としては、以前頼んだのと同じ1.5L入り12本入りを頼んだのですが、気付かずにオーダーの際に1.5Lの1本のオーダーをしてしまっていました。すると、通販会社が「12本入りの間違いではないのか、もしそうなら、そのように配送するけれど」、と連絡してきてくれたので、「その通り、12本入りが欲しいのよ」ということで、12本入りの配送の手続きをしてくれることになりました。とこらが届いてびっくり。8オンス(200mlちょっと)入り48本が届いたのです。そこで、「頼んだのと違うものが届いたけど」と連絡すると、「では1.5L12本入りを再度送ります。間違って届いたものもどうぞ。」ということで、最終的にその2日後に本当に欲しかった飲料水とプラスアルファの飲料水を手に入れました。これは一例ですが、社会の作り方が、『基本的に人は間違えるものだ。間違いがあればその時に主張して修正すればよい。』ということをベースにしているように感じます。洋服などを買っても、払い戻しは(ルールはあるにしろ)簡単にしてもらえるそうです。日本は、間違いをほとんどないようしているので、その後の面倒なやり取りがなくていいのですが、その一方で、間違えないように事前に汲々としなくてはならない、あるいは間違えたことに対して冷淡ということがあるように思います。こちらは、間違いに対して鷹揚なので変更の申し出が気楽にできるのに対して、時間をかけて主張をしなければならない。どちらにも一長一短があります。違った世界観の中で暮らしているのだと、感じます。
ニューヨークに来て、はや2か月がたちました。
生活のセットアップとともに、大学や他の機関で開催されている様々な学術的セミナーなどに参加しているうちに、あっという間に日々が過ぎていった2か月でした。他方で、いろいろな方と新たに知り合いになり、本当に新しいことだらけの日々を過ごしています。
ニューヨークの天気は、ずいぶん例年とは異なるそうです。4月が大変あたたかくて、例年では4月末から5月上旬に咲く桜が、私が到着した4月上旬にはすでに満開で、4月半ばには散っていた一方で、5月の下旬になっても、最高気温が10度から15度の寒い日が続いたりします。こちらに以前から住んでいる方に聞くと、この冬は暖冬で、雪は一度か二度しか降らなかったとのことですし、天候の変動は、日本のみならず、世界中で起きているのだなぁ、と感じます。
食べ物ですが、日本食に関して言えば、お寿司が「SUSHI」として定着しており、たいていのスーパーマーケットの一角にも、アメリカンなレストランのメニューとしても登場しています。でも、酢飯ではないような・・・
先日、知り合ったアメリカ人と料理の話をしていても、
「僕も日本料理は作ったことあるよ。巻きずしを作ったんだ。でも、具材は日本ぽくなかったかも。ポテトとか。」
「うわっ。それは、もう日本の寿司ではないね」
「あっ、でも、日本の寿司らしいものも具材につかったよ。アボカドとか」
「アボカドは、日本スタイルじゃなくって、カルフォルニアスタイルなんだよ」
「そうなの!?」
SUSHIは、もう日本食ではないですね。
(2012年6月10日)
 |
4月に初めて大学へ行った日に、大学のモニュメンタルな建物(旧法学図書館)前でとったものです。 |
この4月から1年間、ニューヨークにあるコロンビア大学の日本経済経営研究所(Center on Japanese Economy and Business)で、客員研究員として研究をしてきます。
大学の教員は、教育とともに研究を通じて社会に貢献することが求められています。そのため、跡見学園女子大学では毎年、何人かの教員が国内・海外の大学や研究機関で学べるよう機会を与えてくれます。今回は、この制度を利用して渡米をします。
私は経済学を専門としていますが、特に、金融の仕組みが不況や好況といった景気の変動にどのように影響しているのか、また景気の変動を小さくするためにはどのような制度設計が必要なのか、ということに興味があります。リーマンショック以降、アメリカでは、こうした問題に対して多くの研究が蓄積され、かつ現在も進められています。
今回の機会に、最先端の研究成果に触れ、自分自身が経済の重大な問題の解決に貢献できるよう、力をつけてきたいと思っています。
2012年3月30日
櫻川幸恵

家庭や企業、団体といったグループや組織は、それぞれの目的のために様々な活動を行います。しかし、すばらしい目的があっても、それを実行するためのお金がなくては、目的も絵に描いた餅にすぎません。目的を実現させるために必要となる「金融」について学びましょう。
専門:マクロ経済学
研究テーマ:信用制約にある経済の特徴
担当授業:消費経済論、金融の基礎、資産運用論、金融システム論、証券論、公共経済学
著書
|
林 文夫 編(2007)『経済停滞の原因と制度 [経済制度の実証分析と設計]』勁草書房(共著)
|
 |
|
内閣府経済社会総合研究所企画・監修、池尾和人編集(2009)『不良債権と金融危機 』慶応義塾大学出版会(共著)
|
 |

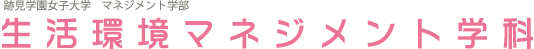
.gif)